「生きる」を創るエコシステムに関する取り組み
キャンサーエコシステムの構築に向けた取り組み
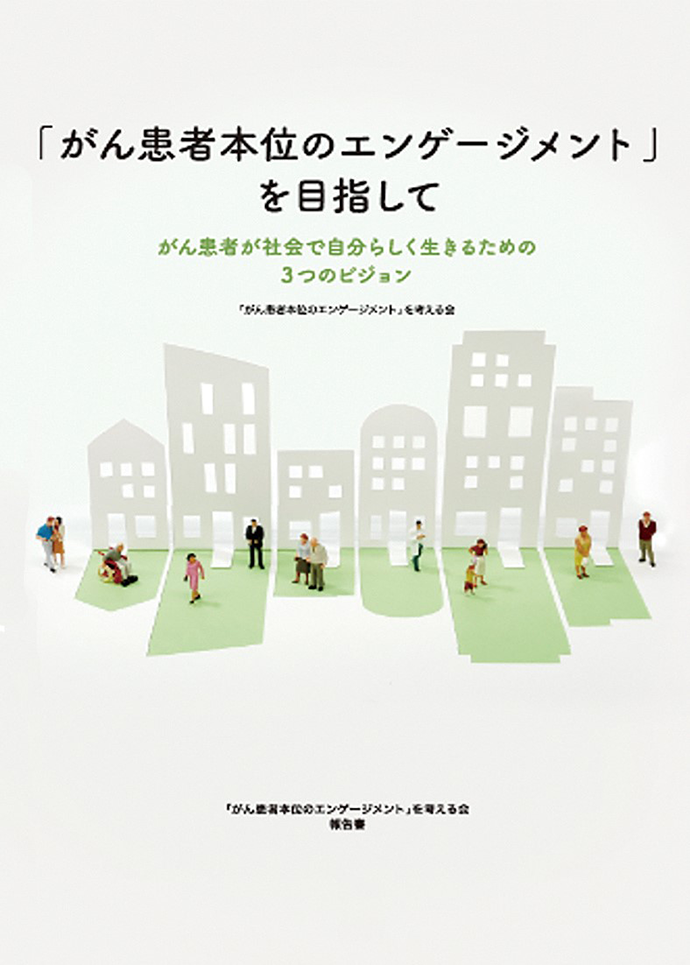
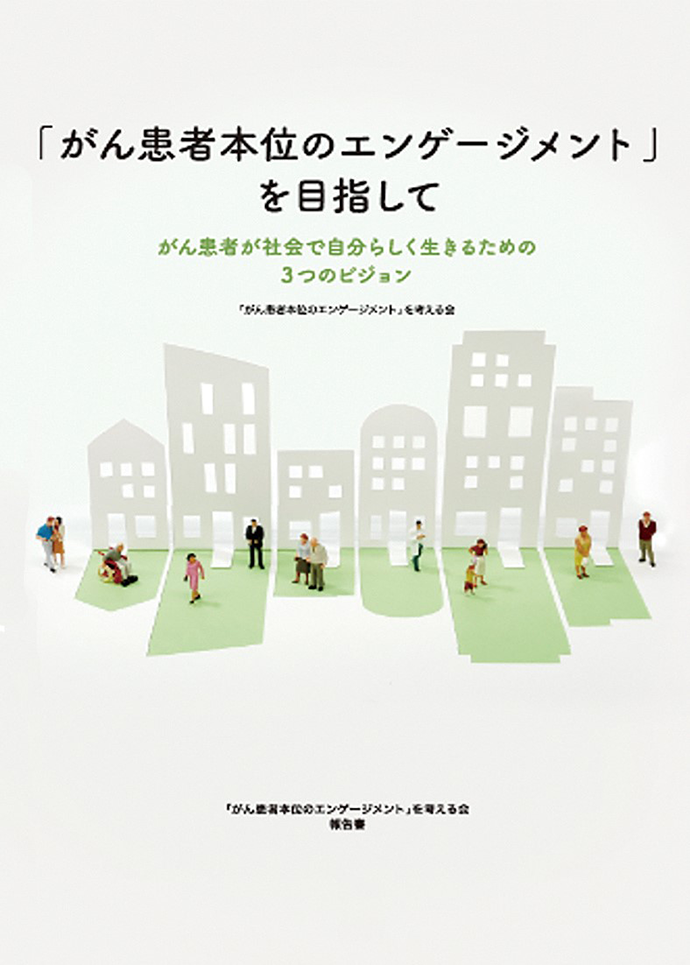
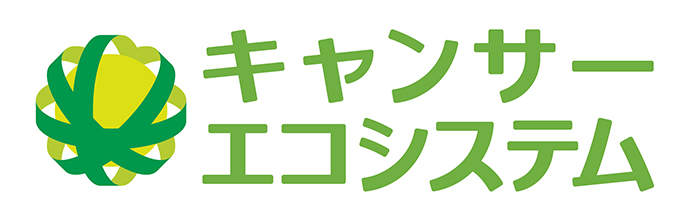
「『がん患者本位のエンゲージメント』を考える会」(以下、本研究会)の議論をまとめた書籍「『がん患者本位のエンゲージメント』を目指して~がん患者が社会で自分らしく生きるための3つのビジョン~」が、2021年1月に株式会社日経BPから発行されました。本書は、本研究会ががん患者とそのご家族が抱えるさまざまな悩みや問題(ペインポイント)について、2018年5月の発足から約2年にわたり議論してきた内容を提言としてまとめた報告書で、当社は本研究会の事務局を務めました。
当社は、本書で提言されている3つのビジョンと10のアクションの実現・実行に向けて、がん患者を取り巻く社会的課題を包括的かつ総合的に解決するためにキャンサーエコシステムの構築に取り組んでいます。
本書で提言されている3つのビジョンと10のアクション
- ビジョン1 社会全体でがん患者を生涯にわたって支える
-
- 1さまざまな関係者による相談機会や情報の積極的な提供
- 2がん患者の状況や悩みに応じた「開かれた相談の場」の提供
- 3がん患者への就労支援と経済的支援制度の周知
- ビジョン2 一人ひとりが安心して納得できる医療/ケアを受けられる
-
- 4さまざまな医療者によるがん患者本位のコミュニケーションの実現
- 5病院内におけるチーム医療の普及と定着
- 6地域における終末期を含めた総合的なケアの提供
- 7一人ひとりに合わせたがん医療の普及と周知
- ビジョン3 がん患者が主役となって自分らしく生きるための素養とスキルを身に付ける
-
- 8医療/ケアを受ける時の基本的な素養の習得
- 9正しい医学情報を提供する仕組みと場の整備
- 10がん教育の普及と充実
キャンサーエコシステムの構築に向けた取り組みの概要
- 「開かれた相談の場」への支援
- がんになっても自分らしくあるために、不安や寂しさなどを受け入れ、精神的に支える「開かれた相談の場」が社会に必要と考えています。当社では、認定NPO法人マギーズ東京(東京都江東区)や認定NPO法人がんとむきあう会が主催する「元ちゃんハウス」(石川県金沢市)などの「開かれた相談の場」の取り組みに対して、アソシエイツとともに支援しています。
- 小児がん・AYA*世代がんの啓発と支援
- 小児がんへの理解促進のため、アフラック・ハートフル・サービス株式会社と共同で、小児がんに関する講演活動や情報発信などの啓発活動を行っています。また、罹患者が少なく世の中での認知が少ないAYA世代のがんについて、「AYAがんの医療と支援のあり方研究会学術集会」をはじめとするさまざまな活動を支援することで、社会に対するAYA世代がんの啓発に取り組んでいます。
- *思春期・若年成人(一般的に15歳から39歳)を指し、AYAはAdolescent and Young Adultの略称であり、特にがん医療において用いられる言葉
- 調布市産学官連携がん啓発プロジェクト(CAJプロジェクト)への参加
- 東京都調布市は、2019年に「調布市がん対策の推進に係る条例」を制定し、さまざまながん対策施策を推進しています。2024年度には、調布市、調布市相互有好協力協定締結大学、民間企業の産学官連携体制によりがん啓発に取り組む「調布市産学官連携がん啓発プロジェクト(CAJプロジェクト)」が設置され、当社はそのメンバーとして参加しました。2024年度は、市の課題である若年層の子宮頸がんをテーマに、参加学生を中心に若者に訴求するキャッチコピーを検討し、そのキャッチコピーに基づいた啓発動画、ポスターを制作しました。併せて、参加学生に対しては、医療従事者やがん経験者による講義を通じ、がんに対する正しい知識の普及啓発に取り組みました。
制作した動画、ポスターは、調布市役所や各公共施設、「20歳のつどい」などの市のイベント、「市報ちょうふ」をはじめとする市の刊行物、市公式ホームページ、SNSなどの広報媒体のほか、市内医療機関、商業施設、協定締結大学などを通じて調布市内にて広く展開され、若年層への子宮頸がん啓発につなげることができました。
- がんに対する正しい理解促進の取り組み
- がんに対する正しい理解とがんの「早期発見・早期治療」の大切さを知っていただきたいという想いで、いつでもどこでもがんについて学べるWeb版「なるほどなっとく がんを知る教室」をリリースしました。「がんの国語」「がんの算数」など、学校の教科ごとにがんの基本的な情報を解説するコンテンツや、学習指導要領に則した「がんのクイズ」などのコンテンツを通して、分かりやすくがんについて学ぶことができます。また、学校においてがん教育が義務化される中、大人にもがんに対する正しい知識を届けることを目的に、放射線治療・緩和ケアの専門医と「大人も子どももがんを知る本」を作成しました。2人に1人ががんになる時代を生きるために必要な知識、がん就労支援の重要性、HPVワクチン、オプジーボ等の最新の薬物治療法や「心の痛み」のケアなどについて分かりやすくまとめており、教職員への研修会やがん検診受診の推進の場などで活用しています。
- 「がん教育」を通じた地域社会におけるがん啓発活動
- 文部科学省による新学習指導要領へのがん教育の実施に関する事項の明記、そして政府によるがん対策推進基本計画における外部講師を活用したがん教育の推進が図られているなか、学校におけるがん教育や教職員向けのがん教育を積極的に支援しています。
小中学校や高等学校さらには大学において、地方自治体や教育委員会と連携し、がん罹患経験のある当社社員や外部講師(経験者・医療従事者)によるがん教育を実施し、がんに関する正しい知識や命の大切さを伝えるとともに、生徒を通して保護者や地域の方々へのがんの理解促進を図っています。
また、教職員におけるがん教育のリテラシー向上を目的に、日本養護教諭教育学会学術集会において、小児がん経験者の講演会を実施し、さらに地域の養護教諭向け研修会では、教職員を対象としたがん教育のモデル授業を開催し、教職員に向けたがん教育を推進しています。
職域におけるキャンサーエコシステムの構築に向けた取り組み
当社は、株式会社日立製作所およびGlobalLogic Japan株式会社との協創を進めており、がんを取り巻く社会的課題に対して企業が従業員とご家族を包括的にサポートする「職域版キャンサーエコシステム」の構築を目指しています。これまでに、日立製作所の職域をフィールドに、がんに罹患した従業員に対するインタビューを実施し、日立グループの職域ステークホルダーが集まり、「ありたい姿」を議論するアイデア検討ワークショップを開催したうえで、次につながる具体的な施策を立案しました。引き続き、がんの罹患前から罹患後まで、がんを経験する当事者のサバイバージャーニーに寄り添い伴走する職域版キャンサーエコシステムの構築に向け、協創の取り組みを進めていきます。
介護エコシステムの構築に向けた取り組み

当社は、今後ますます高齢化が進む日本社会において「『生きる』を創る。」の実現を目指すうえで、がん同様に社会的課題が大きいとされる介護の領域においてもエコシステムの構築を目指し、2024年より介護エコシステムの構築に向けた活動を開始しました。
2024年には介護当事者(被介護者とご家族)を取り巻く、身体的・精神的な問題、さらには就労や経済面を含めた社会的課題を、徹底したデザイン思考で明らかにし、介護エコシステムの構築に向けた「3つのビジョンと10のアクション」を策定しました。
2040年の日本社会はさらなる高齢化と人口減少の加速が予測され、社会保障費の増大や地方の過疎化、介護や医療の担い手の不足など多様な課題に直面することになります。このような社会の到来に向け、当社は「3つのビジョンと10のアクション」を通じてさまざまなステークホルダーとの連携・協業を進め、社会的課題の解決に向けた取り組みを実践していきます。
3つのビジョンと10のアクション
- ビジョン1 当事者が最期まで自分らしく生きがいを感じ、相互に支え合う社会
-
- 1現代的なつながりを創り出すコミュニティの形成により、孤独・孤立を生み出さない環境の整備
- 2当事者が自らの役割を感じられる仕組みと場の提供
- 3当事者に最期まで寄り添う伴走サポートの実践
- ビジョン2 当事者にとってより望ましいケアの実現に向けた包括的サポート
-
- 4事柄別でなく当事者に丸ごと寄り添う相談体制の整備
- 5多職種間のシームレスな連携が進む、当事者を中心とした環境の整備
- 6日常における地域住民のかかわり合いの中で実践するケアの拡大
- 7介護・医療需要の増大による避けられない在宅ケアへの備えと生活モデルの実践
- 8家族をはじめとしたケアラー支援の普及と充実
- ビジョン3 誰もが自らの人生と向きあう中で介護を自分事化する
-
- 9高齢者ニーズの変化を捉えた、介護に対する国民理解の促進
- 10介護への備えの機会の提供と実践のサポート
この「3つのビジョンと10のアクション」を通じて、皆様に介護をもっと身近なものと感じていただきたいという想いを込め、「暮らしのなかにある介護」の実現を目指していきます。
スタートアップ企業との共創
当社は、「『生きる』を創るエコシステム戦略」の実現に向けて、子会社であるAflac Ventures Japan株式会社が運営するCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)ファンド*を通じ、スタートアップ企業への機動的な投資を推進しています。これまでに約30社(2025年9月末時点)に投資を実行し、スタートアップ企業との共創による新たな価値の創造に取り組んでいます。
- *自社の事業との相乗効果を得ることを目的に、主に未上場のスタートアップ企業に投資を行なうファンド
